



中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。
中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。
身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。
ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。
このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。
この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。
中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。
のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。
中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。
身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。
ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。
このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。
この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。
中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。
 弁証論治概要
弁証論治概要症状・所見→四診→証→治法→方剤
肝腎陰虚
次の症状のいくつかある方は、芍薬甘草湯が良く効く可能性が大きいです。
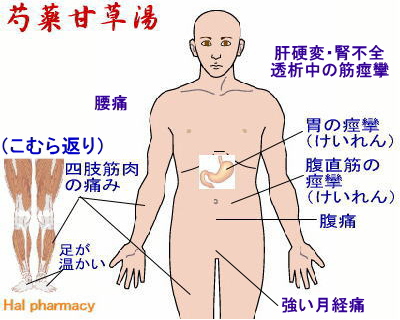
 八法(治法の8分類)
八法(治法の8分類)芍薬甘草湯は、和法:和解あるいは調和の作用によって病邪を消除する治法です。
【中薬大分類】和解剤…調和を行う方剤です。和解の方法により病邪を解除する方剤です。少陽半表半裏の邪を解除したり、肝脾不和・脾胃不和を改善するもので、八法の【和法】に相当します。
【中薬中分類】調和肝脾剤…肝と脾を調和する方剤です。肝気欝結による脾胃への横逆、または脾虚不運で肝陰が不足して疏泄が失調した脾虚肝乗により、胸脇脹痛・腹痛・悪心・嘔吐・下痢など肝胃不和・肝脾不和が見られるときに使用します。
【気血津・臓腑証】
筋痙攣・痙攣痛(きんけいれん・けいれんつう)…白芍と炙甘草からなり、いずれも平滑筋・骨格筋の痙攣(けいれん)を緩解して鎮痛する効果をもち、一般には鎮痙・鎮痛剤として頓用されます。
筋のけいれんは、肝血・肝陰が不足し肝気が抑制されなくなって失調し、筋脈を擾乱するために生じると考えられています。白芍は補血薬で、肝血を補うことにより肝の疏泄を調整します(陰液を滋潤することにより陽気を安定させます)、この効能を柔肝(平肝)と呼んでいます。灸甘草は補気により白芍の吸収を補助し、かつ生津の効能により肝陰の滋潤を補助するので、柔肝の効果を高めることができます。以上のように、間接的な疏肝解欝剤と考えるとよいです。それゆえ、疏肝解欝に関連する多くの方剤に基本薬として配合されています。
なお、柔肝の白芍と健脾の炙甘草の組合せであり、脾を強め肝血を滋潤して柔肝するので、「脾虚肝乗」の肝脾不和にも適合します。桂枝加芍薬湯・小建中湯・黄蓍建中湯・当帰建中湯などもほぼ同様の配合であり、脾虚肝乗に使用してよいです。
 中医学基礎知識
中医学基礎知識●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。
 五臓(ごぞう)
気・血・津液・精
弁証論治・事典
五臓(ごぞう)
気・血・津液・精
弁証論治・事典
【証(病機)】肝陰虧損・筋脈攣急(かんいんきそん・きんみゃくれんきゅう)
【中医学効能(治法)】 平肝・解痙止痛・柔肝
【用語の説明】(term)
 平肝(へいかん) »…肝の機能亢進状態を改善することです。
平肝(へいかん) »…肝の機能亢進状態を改善することです。
 止痛(しつう) »…痛みを止めることです。
止痛(しつう) »…痛みを止めることです。
 攣急(れんきゅう) »…「ひきつけ」のことです。
攣急(れんきゅう) »…「ひきつけ」のことです。
 柔肝(じゅうかん) »…肝の機能を高めることです。肝血を補い、肝気を伸びやかにし回復させることです。
柔肝(じゅうかん) »…肝の機能を高めることです。肝血を補い、肝気を伸びやかにし回復させることです。
 証の判定
証の判定
証(症状・体質)判定を望む方 は
証判定メニュー
は
証判定メニュー
※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。
●横紋筋や平滑筋の異常緊張や痛み
●四肢のひきつれ
●両腹直筋のつっぱり
![]() 【舌診】(tongue)
湿潤、時に薄い白苔を見ます。
【舌診】(tongue)
湿潤、時に薄い白苔を見ます。

![]() 【脈診】(pulse)
弦遅です。
【脈診】(pulse)
弦遅です。
![]() 【腹診】(abdomen)
両側の腹直筋(特に右側)が拘攣(こうれん)します。
【腹診】(abdomen)
両側の腹直筋(特に右側)が拘攣(こうれん)します。
次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
| 成人(15歳以上) | 1包(1.875g) | 2回 |
| 7歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 4歳以上 7歳未満 | 1/2包 | |
| 2歳以上 4歳未満 | 1/3包 | |
| 2歳未満 | 服用しないでください | |
<用法・用量に関連する注意>
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

|
 構成生薬の説明
構成生薬の説明
芍薬(白)・甘草(炙甘草)は、骨格筋・平滑筋のけいれんを強く抑制して、鎮痛に働きます。また、鎮静作用もあります。
このほか栄養・滋潤作用をもっています。
(補足)
本方は肝の陰血を補うことによって柔肝し、筋脈を濡養して疏泄を正常に行わせる働きがあり、鎮痙・鎮痛の基本処方として多くの処方に配合されています。
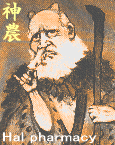 芍薬と甘草だけの、ごく簡単な構成ですが、芍薬には筋肉の拘攣を緩解する作用があり、甘草の緩和作用と相まって、鎮痛・鎮痙効果を発揮します。
芍薬と甘草だけの、ごく簡単な構成ですが、芍薬には筋肉の拘攣を緩解する作用があり、甘草の緩和作用と相まって、鎮痛・鎮痙効果を発揮します。
いずれも補性・潤性ですから、虚証で燥証向きと言えますが、熱証・寒証、実証・虚証に関係なく、広く鎮痛・鎮痙の目的で用いることができます。
| 生薬名(herb name) | 薬量(quantity) | 君臣佐使(role) | 効能1 | 効能2 | 効能3 | 効能4 | 大分類 | 中分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芍薬 » | 6 |
君薬 |
止痙 |
止痛 |
柔肝 |
補血 |
補虚薬 |
補血薬 |
| 甘草 » | 6 |
臣薬 |
止痙 |
止痛 |
生津 |
補気 |
補虚薬 |
補気薬 |

 処方の副作用
処方の副作用水分の代謝の悪い方が服用すると、排尿困難やむくみなどが起こることが、まれにあります。
 使用上の注意
使用上の注意
【妊娠・授乳の注意】![]()
●妊婦または妊娠の可能性のある人は、使用できない場合があります。
 補足説明
補足説明